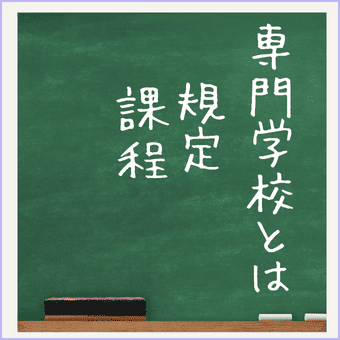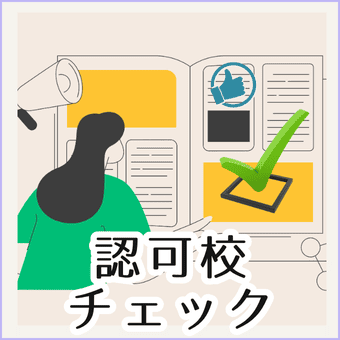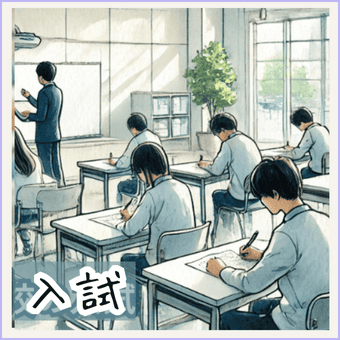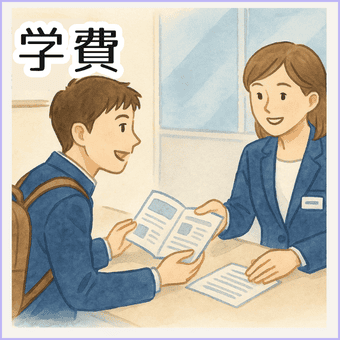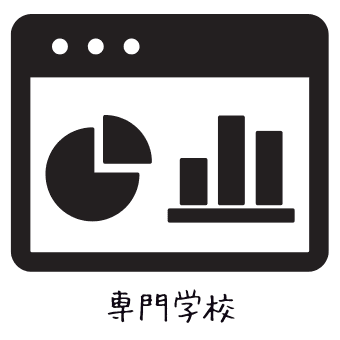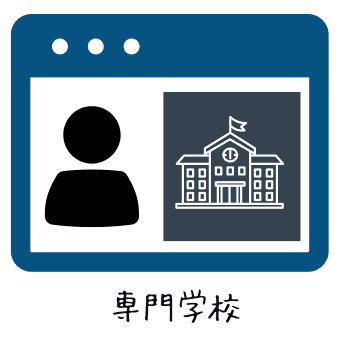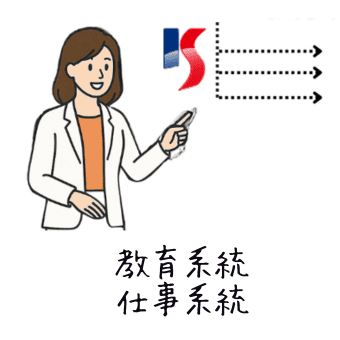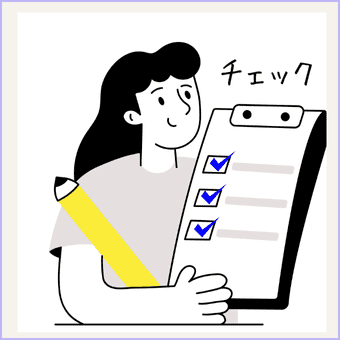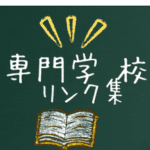進学ガイド掲載情報一覧
専門学校進学ガイド > 専門学校進学ガイド掲載情報一覧
※ 進学ガイドの掲載情報
▸専修学校と専門学校
▸専門学校の認可校
▸専門学校の設置者
▸専門学校の運営と規模
▸専門学校制度の歴史
▸資料;複数校運営の専門学校

資料
専門学校の学び:分野、課程など
▸専門学校の教育分野
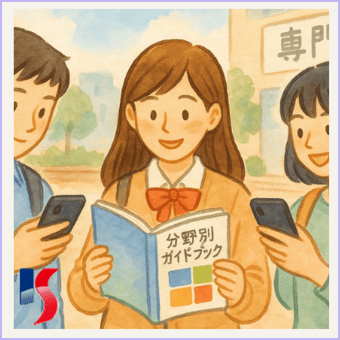
教育は8つの分野に分類されています。入学者が最も多いのは文化教養です。
▸専門学校の教育課程
▸専門学校と資格
▸専門学校と大学の比較
入試・学び費用など
▸専門学校の入試
▸専門学校の学費
▸修学支援制度学生生活支援制度
- 専門学校の検索方法
仕事、教育分野、地域別など
専門学校の情報収集
- 学校公式ホームページの利用方法
常に最新情報が更新されています - パンフレット入手のオススメ
資料請求の方法 - 説明会・オープンキャンパス
内容確認・参加方法など
データで見る専門学校
その他・関連情報
ホームページの位置
┝ 日本の専門学校
└└ 専門学校進学基本チェック